
a) 合掌造り家屋の形態と構造
合掌造り家屋の大きな特色の1つは、柱や桁、梁で構成される軸組部と叉首台(ウスバリと称する)から上の小屋組部が、構造的にも空間的にも明確に分離されていることである。
日本の一般的な民家では、上部の構造を支える束が軸組部を構成する桁や梁から立ち、あるいは柱や桁に仕口を造って組まれた梁が叉首台を兼ねるなど、軸組部と小屋組は構造的に繋がり、明確には分離されていない(図6-2、3、4)。また、土間や居室では、天井を設けずに軸組部の空間が小屋組部まで吹き抜けとなっていて、下から小屋組と屋根裏が見えるものが一般的である。これに対して、合掌造り家屋では、下屋を除く主軸部の上部は桁と梁で一旦、平坦に組み上げられ、その上に叉首台を置き並べて叉首を組む構造であり、軸組部と小屋組は構造的に明確に分離されている(図2-1、2、3)。また、土間の上部や居室の上部を吹き抜けにすることはない。これらのことは、他の地方に見られない合掌造り家屋の大きな特色である。
この軸組部と小屋組部の構造的な明確な分離は、合掌造り家屋の建築の方法に関わっている。つまり、この地方では、軸組部は専門的な技術を持った大工の仕事であるが、礎石の据え付けと小屋組部と屋根の材料の確保、加工、組み立て、葺き上げは、伝統的な互助制度である「ユイ」で行われることによっている。したがって、軸組部の部材は台鉋等によって丁寧に仕上げられ、多種の仕口や継手によって組み立てられるが、小屋組と屋根は、丸太材のままか斧や手斧による粗い仕上げとなり、部材の組み立ても稲縄やマンサクの木や蔓のようなもので結ぶだけとなっている。
軸組部については建築の費用が必要であるが、小屋組と屋根については費用が必要でないという制度は、現金収入を得ることの少なかった山村の経済的条件から生じた生活の知恵である。こうした、専門的な仕事と相互扶助による仕事の明確な分離も、この地方独特のものであり、他では見られないものである。なお、この地方のような山深い山村では、大工が独立して生計が立てられるほどの経済的な余裕はなかったので、専門的な大工は存在せず、家を建てるときには、他の地方から大工を呼び寄せて造らせていた。
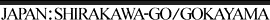

![]()