
d) 平面の規模と形態
合掌造り家屋は他の地方の民家に比較して、規模が大きいといえる。江戸時代末期から明治時代頃の民家の標準的規模は梁間3間〜3.5間、桁行4間〜6間程であったと考えられる。これに対して、白川郷と五箇山地方の合掌造り家屋は、小規模のものでも梁間3.5間、桁行7間程であり、庄屋クラスの大きな家屋では梁間7間、桁行12間を超える例も見られ、日本の一般的な民家に比べて規模が大きいといえる。合掌造り家屋の規模が大きい理由は、両親とその長男夫婦と弟姉妹たちが分家しないで1つの家屋で生活する大家族制のためと考えられたこともあった。しかし、大家族制はこの地方の特定の集落に見られるが、全ての集落に見られるものではないので、現在の学説では、これだけをその理由としていない。これに代わり、最も説得性のある説は、この地方で生産されていた塩硝に関わるものである。この地方では家屋の床下に穴を掘って、ヨモギなどの草を詰め、下肥などで発酵させて硝土を作っていたので、広い床面積を必要としていた。なお、養蚕の隆盛による広い小屋裏空間の要求も、家屋の規模を大きくする要因の1つになっていたと推測することはできる。
平面は土間の部分と床上部に分けられる。床上部は居間と接客室、仏間、寝室の4室から構成されるのが基本で、規模が小さい場合には居間と接客室が1室となり、大きい場合には、さらに上級の接客室である座敷や寝室、収納室などが付け加えられる。これらの部屋の構成は、白川郷と五箇山地方の間でも特に相違は見られない。
出入口の取り方と土間部の構成については、白川郷と五箇山地方では相違が見られる。白川郷の多くの合掌造り家屋では、出入口は居間の平側に設けられる。一方、五箇山地方では妻側に半間ほどの下屋を造り、その中央寄りに出入口を設ける場合が多い。そして、多くは下屋の屋根も茅葺きとし、大屋根との取り合いを葺き回すので、一見、入母屋風屋根となり、平側に出入口を設ける白川郷の合掌造りとは異なった外観となっている(図1-1、2)(現在は、改造されて鉄板葺きとなっているものが多くなっている)。
土間部は牛馬を飼う厩と炊事場からなる。炊事場では炊事の他に脱穀や紙漉きなどの作業も行われていた場所で、白川郷ではこの部分に床が張られていて、土間となる五箇山地方の場合と相違している。
合掌造り家屋の平面のうち、床上部の部屋の構成は日本の民家に一般的に見られるものであり、この地方に特色的なものではない。しかし、土間部は一般の農家では広い土間を取り、そこでさまざまな作業が行われるのに対し、合掌造り家屋の土間は狭い。これは敷地が狭い山間部の農家に共通して見られる特色であり、特にこの地方に限られた特色とはいえない。
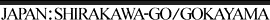

![]()