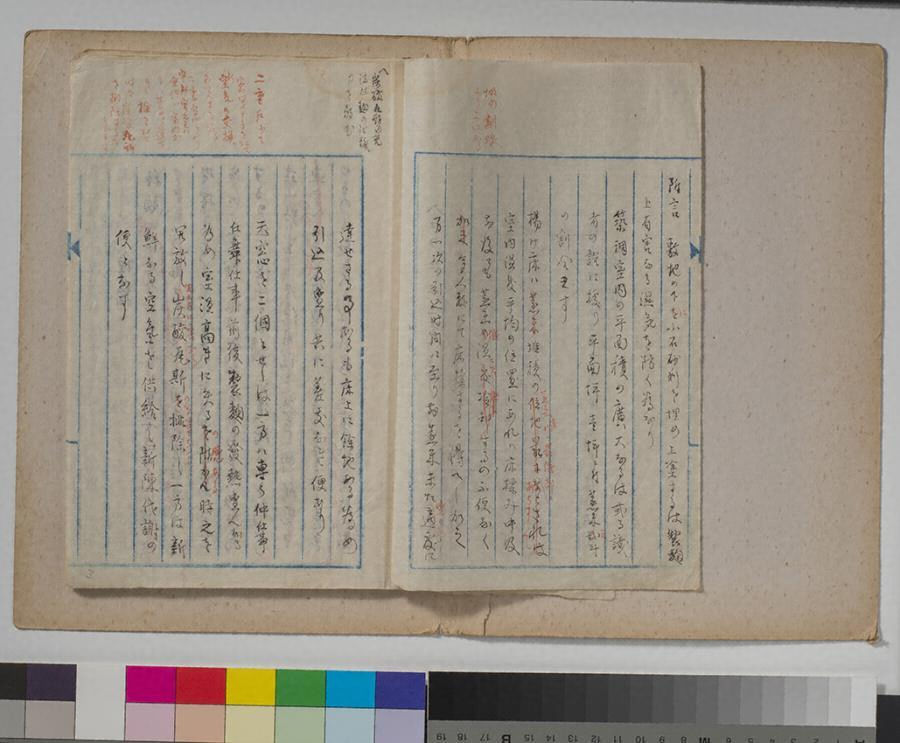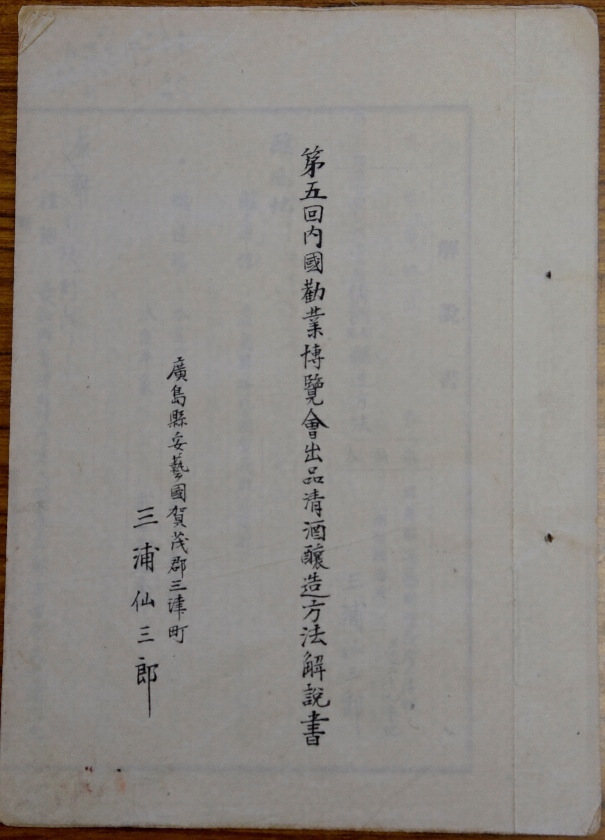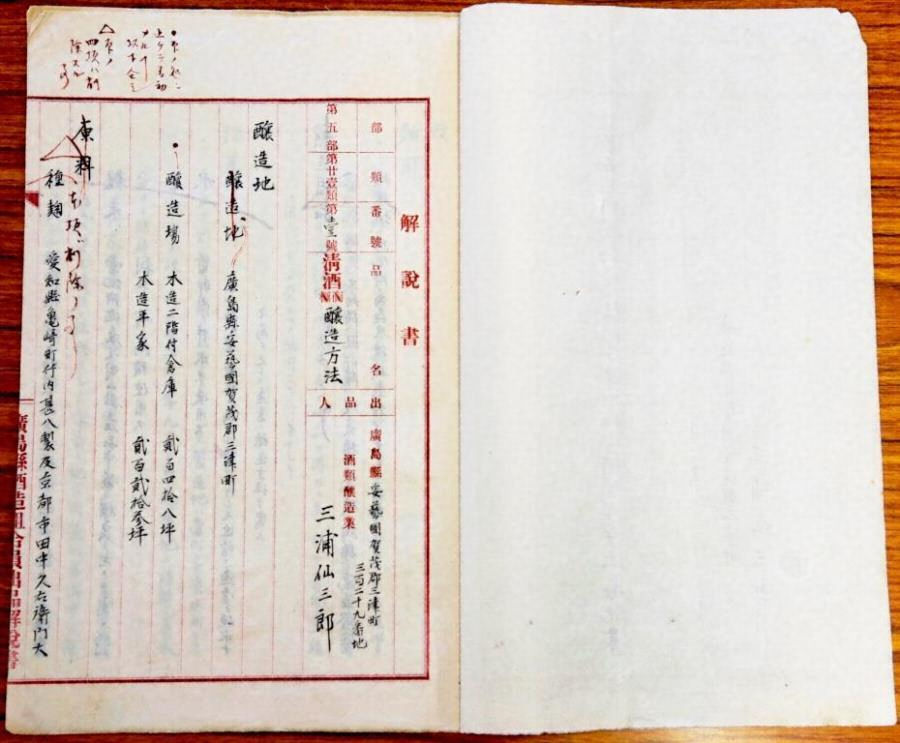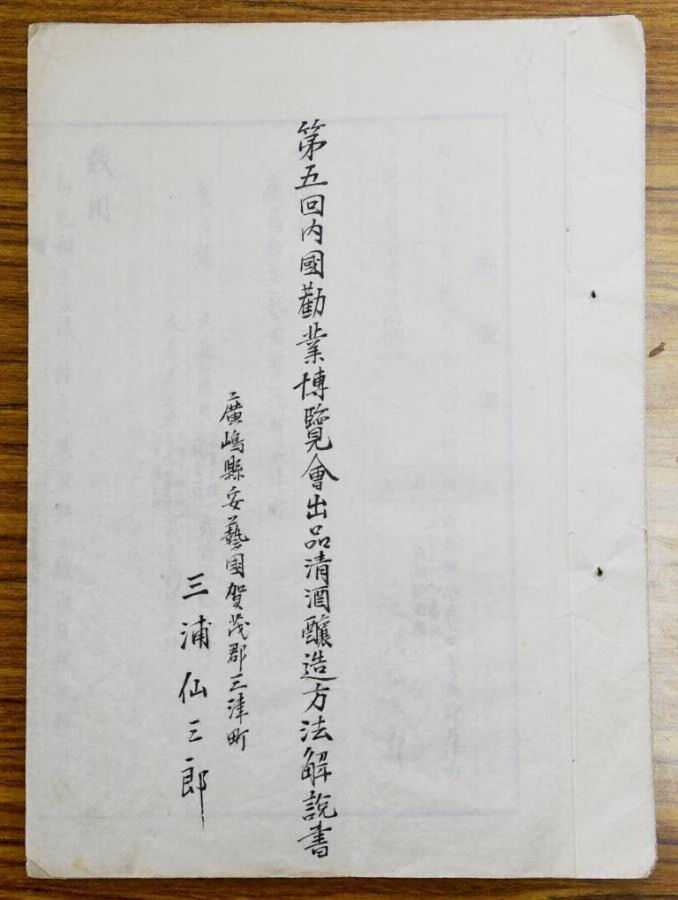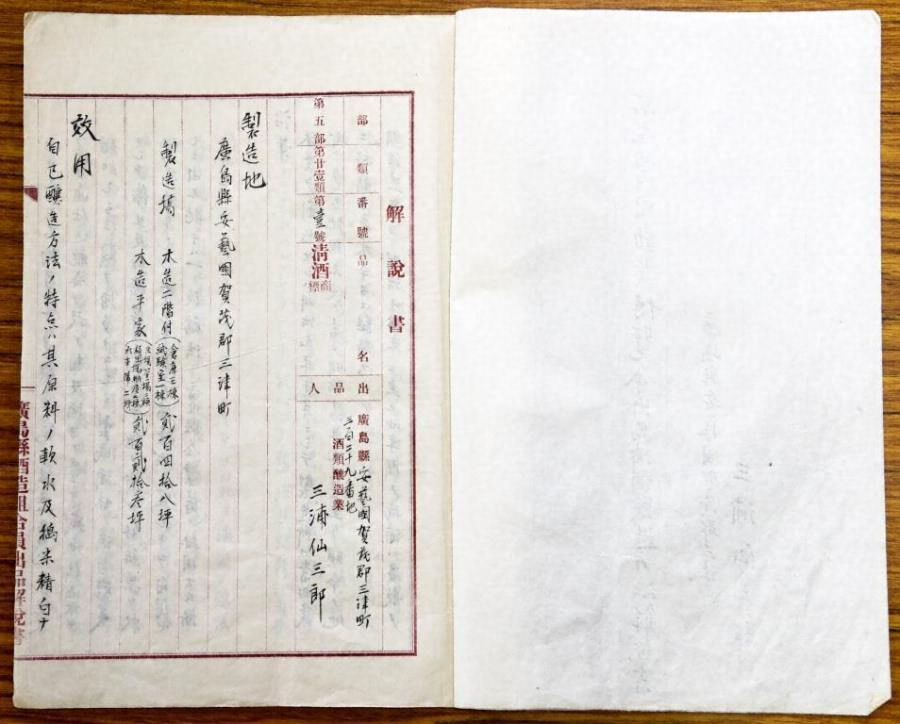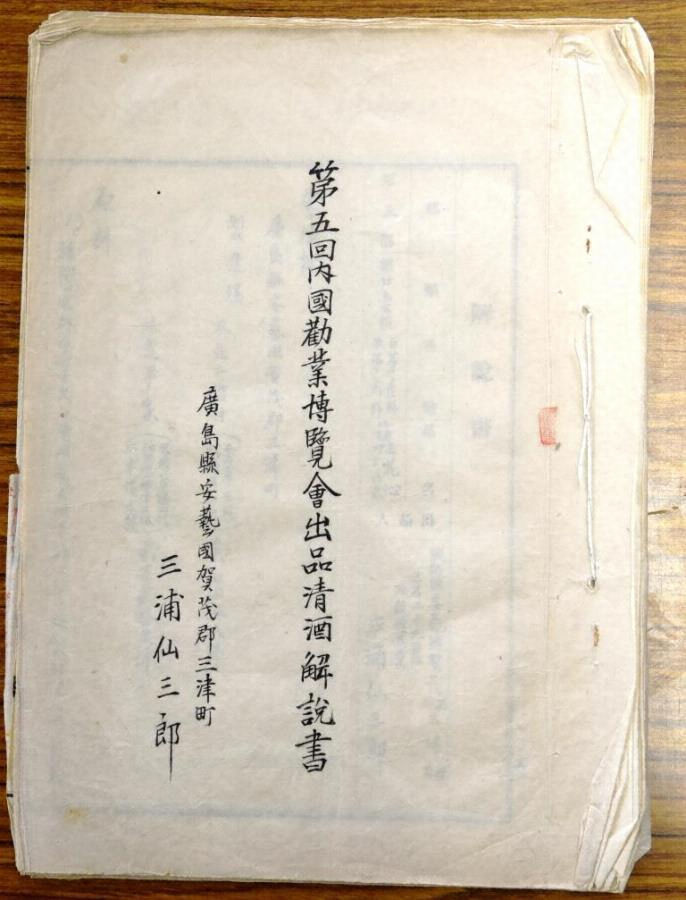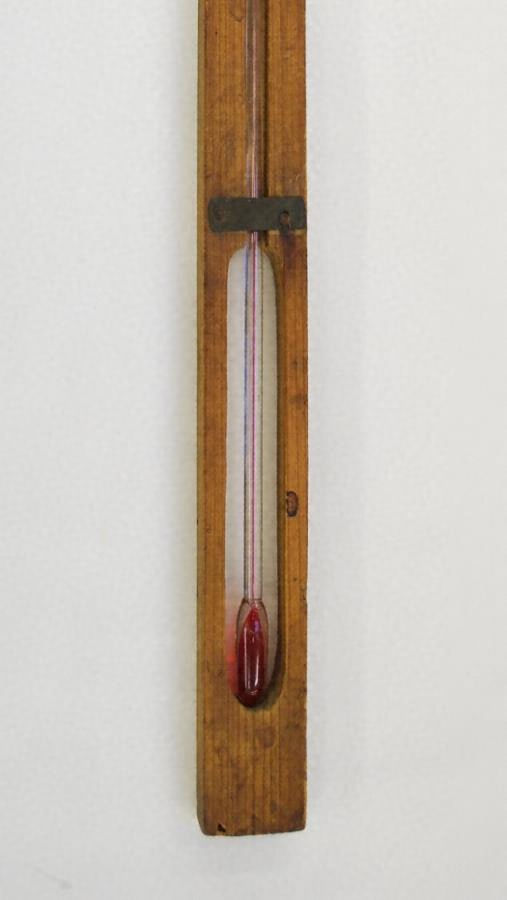三浦仙三郎酒造関係資料
① 改醸法実践録(草稿)
② 履歴書(草稿)
③ 第五回内国勧業博覧会出品清酒醸造方法解説書(明治35年10月草稿)
④ 第五回内国勧業博覧会出品清酒醸造方法解説書(明治35年12月草稿)
⑤ 第五回内国勧業博覧会出品清酒解説書(草稿)
⑥ 赤液温度計
みうらせんざぶろうしゅぞうかんけいしりょう
概要
三浦仙三郎酒造関係資料
① 改醸法実践録(草稿)
② 履歴書(草稿)
③ 第五回内国勧業博覧会出品清酒醸造方法解説書(明治35年10月草稿)
④ 第五回内国勧業博覧会出品清酒醸造方法解説書(明治35年12月草稿)
⑤ 第五回内国勧業博覧会出品清酒解説書(草稿)
⑥ 赤液温度計
みうらせんざぶろうしゅぞうかんけいしりょう
広島県
明治
①紙、墨
②紙、墨
③紙、墨
④紙、墨
⑤紙、墨
⑥ガラス、木
①40×27.5㎝、2ツ折
②40×27.5㎝、2ツ折、39g
③40×27.5㎝、2ツ折、20g
④40×27.5㎝、2ツ折、19g
⑤40×27.5㎝、2ツ折、20g
⑥全長95.2㎝、全幅2.6㎝、全高1.4㎝、ガラス部長さ78㎝
6点
①広島県東広島市安芸津町三津3734
②~⑥広島県東広島市安芸津町三津4398
東広島市指定
指定年月日:20190426
①株式会社今田酒造本店
②・⑥東広島市教育委員会
③~⑤不詳
有形文化財(美術工芸品)
①は、三浦酒造が現所有者に売却。
②は、三浦氏遺族から東広島市教育委員会に寄贈
③~⑤は、広島杜氏組合が保管
⑥は、安芸津記念病院が収集し、安芸津町歴史民俗資料館に寄贈。市町合併により東広島市教育委員会に移管。